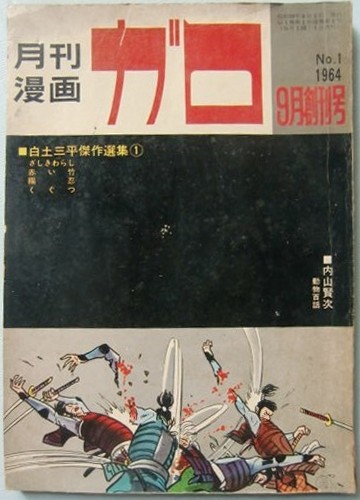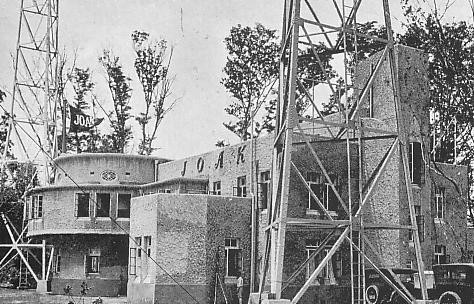国際フレンドシップ・デー
国際フレンドシップ・デーは、国連が定める国際デーのひとつです。2011(平成23)年7月の国連総会で制定されました。英語表記は「International Day of Friendship」。
「ユネスコ未来共創プラットフォーム」のHPより引用します。
「国際フレンドシップ・デー」(7/30)
7月30日は「国際フレンドシップ・デー」です。この国際デーは2011年の国連総会にて、人々、国々、文化や個人の友好関係が平和への努力を促し、コミュニティ間の懸け橋になるという考えのもと宣言されました。
決議では、未来のリーダーである若者を様々な文化や国際理解、多様性の尊重に関するコミュニティの活動に参加させることに重点を置いています。
国際フレンドシップ・デーを記念し、国連は各国政府、国際機関および市民社会団体に、文化間の対話、連帯、相互理解と調和を促す国際社会の努力に貢献するイベント、活動や取組を実施することを奨励しています。
また、本国際デーは「平和の文化」を、暴力を排除し、問題解決を目的として根本的な原因に焦点を当てることで紛争を防ぐ努力に関する価値、姿勢および態度と定義したユネスコの提案に基づくイニシアティブであり、この提案は1997年の国連総会にて採択されました。
平和の文化を促進する行動
教育を通して平和の文化を育む
持続可能な経済および社会の発展を促進する
すべての人権を尊重することを促進する
ジェンダー平等を確保する
民主的な参加を奨励する
理解、寛容、連帯を前進させる
参加型のコミュニケーションおよび情報と知識の自由な流れをサポートする
国際平和と安全を促進する
小学館の「HugKum」より引用します。
「国際フレンドシップ・デー」ってどんな日?
みなさんは「国際フレンドシップ・デー」をご存じでしょうか? フレンドシップとは、日本語で「友情・友愛・友好」を意味する言葉。英語表記は「International Day of Friendship」となります。国際フレンドシップ・デーの成り立ちや日本での取り組みなどを見ていきましょう。
国によって異なる「フレンドシップ・デー」の日付
国連が国際デーとして制定した国際フレンドシップ・デーは7月30日ですが、それとは別に世界各地には友情を祝う記念日があります。たとえば、アメリカやインド、シンガポールやアラブ首長国連邦などでは、毎年8月の第1日曜日。また、メキシコやベネズエラ、ドミニカ共和国、フィンランドなのでは、2月14日をフレンドシップ・デーとして祝っています。
「国際フレンドシップ・デー」の目的・歴史・由来
国際フレンドシップ・デーは、そもそも何を記念に制定されたのでしょうか? 国際フレンドシップ・デーの目的・歴史・由来を見ていきましょう。目的
国際フレンドシップ・デーは、国や文化を超えた友情が、世界平和を促進し、コミュニティ同士を結びつけることを再認識する日として定められました。世界中の政府や国際機関、市民団体などが、文化の違いを超えて対話し、相互理解を深めていくうえで必要な交流を進めていくために、国連は、この記念日を通じて、さまざまな取り組みやイベントの実施を呼びかけています。
また、すべての人々の安全や安心を実現するために、暴力を否定し、異文化間の摩擦などによって生じる問題の解決を図ることも国際フレンドシップ・デーの大きな目的です。
歴史
1930年、グリーティグカード会社「ホールマークカード」の創始者であるジョイス・ホールが行った提案がフレンドシップ・デーのはじまりといわれています。グリーティグカードは、記念日などに恋人や友人など親しい人に感謝や祝福の気持ちを伝えるカードです。当初は、人々にグリーティグカードを送り合うことを勧める商業的な戦略を目的としたものでした。
1958年7月30日、パラグアイで国際的な友情を推進する組織として「世界友情十字軍」が設立され、同時に、国際フレンドシップ・デーの制定が提案されました。
その後、2011年に国連が国際フレンドシップ・デーを国際デーのひとつに制定しました。
由来
国連が国際フレンドシップ・デーを制定した背景には、世界的な貧困や暴力、人権侵害などの問題があります。世界の人々の平和や安全、社会的調和を損なう課題や危機を解決するためには、異なる言語や文化、価値観を持った人々の相互理解や和解が不可欠です。そのもっともシンプルな方法が、友情を育むことです。世界中の人々が友情を育み、その絆を深めていけば、強固な信頼関係を築くことにつながります。
「国際フレンドシップ・デー」の日本の取り組み
国際フレンドシップ・デーは、異文化交流を通じ、世界の人々が友情を深める国際デーです。日本では、どのような取り組みやイベントが行われているのでしょうか。政府や各団体、企業などによる広報・啓発活動
国際フレンドシップ・デーには、政府をはじめ、さまざまな団体や企業が、ツイッターやインスタグラムなどのSNSを活用した広報・啓発活動を行っています。たとえば、東京ディズニーリゾートでは、公式のブログで7月30日の国際フレンドシップ・デーに、世界中に素敵な友情があふれることを願う記事をアップしています。
また国際フレンドシップデーにちなんだグッズも販売しています。記念アイテムには「ミッキー&フレンズがずっと大切にしていること。それはいつも“自分らしく”いること。そして友達の“自分らしさ”を尊重すること。ミッキーたちと一緒に、友達について考え、友達へ感謝の気持ちを伝えよう!」というメッセージが込められています。
国際フレンドシップデーにちなんだイベント開催
国際フレンドシップデーにちなんだイベントも開催されています。2023年は、オンラインイベント「国際フレンドシップデー・ソートストーム」が開かれます。私たちの人生の大切な要素である<友情>というものを改めてよく感じてみて、どんな意図が、そして行動がそれを増やしていくのか、みんなで探求してみましょう。この世界の友情の量を増やすことを考え、イベントを通して、みんなで世界にそんな違いを創り出していこうという楽しい催しです。
「国際フレンドシップ・デー」に、わたしたちができること
世界平和の促進にもつながる国際フレンドシップ・デー、わたしたちにもできることがあります。グリーティグカードを贈る
友達に日頃の感謝を伝えるため、グリーティグカードを贈ってみてはいかがでしょう。お互いの絆を確認し、友情を深めるきっかけになります。また、カードのほかに、花や友情の証になるといわれるリストバンドといった贈り物もおすすめです。
SNSによる国際デーの広報・啓発活動
個人でも国際フレンドシップ・デーの存在や意義を世界に発信することができます。ツイッターやインスタグラムといったSNSを通じて、記念日である7月30日やその前後に友情の大切さを訴えるメッセージを発信してみましょう。
国際交流基金への寄付
「国際交流基金」は、総合的な国際文化交流を行う独立行政法人。海外との文化・言語・対話といった交流事業を柱とする国際交流基金の活動を援助するため、寄付を行うことができます。クレジットカードや銀行振込での寄付が可能です。相手を理解し、敬い、友情を深めよう
国際フレンドシップ・デーは、世界的な友情を育むための記念日です。世界中の人々が交流を深め、強い絆や信頼関係を築くことができれば、暴力や貧困、人権侵害といった問題も解決できるはず。そのためには、世界中の人々が相手の考え方や価値観を理解し、互いに敬うことが不可欠。まずは、身近な友達に日頃の感謝を伝えるためにも、国際フレンドシップ・デーをきっかけにしてみてください。